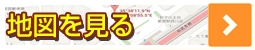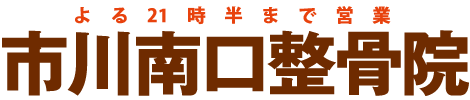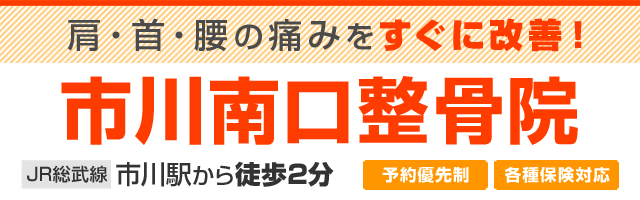こんなお悩みはありませんか?

姿勢が悪く見える
肩こり・首こりがひどくなる
呼吸が浅くなる
バストの位置が下がる
腕や手のしびれが起こることがある
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩は、スマートフォンやパソコンの長時間使用により、前かがみの姿勢が習慣化することで起こりやすく、現代人に多く見られる傾向があります。特にデスクワーク中心の方は注意が必要です。
原因としては背中の筋力の低下だけでなく、大胸筋や小胸筋といった胸の筋肉が硬くなることも挙げられます。そのため、胸を開くストレッチを取り入れることで、巻き肩の軽減が期待できます。
また、肩甲骨の動きが悪くなると、肩が前に引っ張られやすくなるため、肩甲骨を寄せたり、しっかり動かすことがポイントです。さらに、腕を組む、頬杖をつく、片方だけでリュックを背負う、うつ伏せで寝るなどのクセも巻き肩を悪化させる要因となります。
一度身についた姿勢のクセはすぐには変えにくいですが、日々の姿勢を意識し、ストレッチやエクササイズを継続することで、徐々に巻き肩の軽減が期待できます。
症状の現れ方は?

巻き肩が進行すると、さまざまな不調が現れることがあります。
まず、肩が前に出ることで首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、慢性的な肩こりや首こり、さらには痛みを感じやすくなります。特にデスクワークが多い方にみられやすい傾向です。
次に、筋肉の緊張によって血流が悪くなることで、緊張性の頭痛が起こることもあります。
また、巻き肩により胸が縮こまり、背中が丸まって姿勢全体が悪くなることで、見た目にも影響が出やすくなります。
胸が開きにくくなると、呼吸が浅くなり、疲れやすくなったり、酸素供給の低下によって集中力が落ちる場合もあります。
さらに、肩が前に出た状態が続くことで神経や血管が圧迫され、腕や手にしびれを感じることがあります。特にスマートフォンやパソコン作業を長時間行った後に現れやすいです。
巻き肩が進行すると、肩の可動域が狭まり、肩を上げにくくなったり、腕を後ろに回しづらくなったりすることもあります。その結果、服の着脱がしにくくなる場合もあります。
その他の原因は?

巻き肩の主な原因には、日常生活での習慣や筋肉のバランスの乱れが関係していることが多いです。具体的には、いくつかの要因が巻き肩の状態を引き起こしやすくします。
まず、スマートフォンやパソコン作業の増加による前かがみ姿勢が挙げられます。デスクワークやスマートフォンの使用が長時間続くと、肩が前に出やすくなり、巻き肩の原因となることがあります。特にキーボード操作時の腕の位置には注意が必要です。
次に、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)の緊張や柔軟性の低下です。これらの筋肉が硬くなることで、肩が前方に引っ張られやすくなり、巻き肩の状態が定着しやすくなります。ストレッチ不足や筋肉の過緊張が主な要因です。また、背中や肩甲骨まわりの筋力が不足している場合も、肩甲骨の位置が安定せず、肩が前に出やすくなります。特に猫背の姿勢と関連が深いため、注意が必要です。
肩甲骨の可動域が狭くなることも、巻き肩につながります。肩甲骨がスムーズに動かなくなると、肩が固定された状態になりやすくなります。特に運動不足の方は、この状態に陥りやすい傾向があります。
さらに、日常の無意識のクセや生活習慣も原因となることがあります。たとえば、腕を組む、頬杖をつく、リュックを片方の肩だけにかける、うつ伏せや横向きで寝るなどの習慣が、知らず知らずのうちに巻き肩を助長してしまうことがあります。
また、筋力トレーニングの偏りも要因の一つです。胸まわりの筋肉ばかりを鍛え、背中の筋肉を十分に使わない場合、筋肉のバランスが崩れ、巻き肩が進行しやすくなります。トレーニングの際は、背中の筋肉もバランスよく使うことが大切です。
精神的なストレスや緊張も巻き肩に影響することがあります。緊張状態が続くと、無意識に肩に力が入り、肩が前方にすぼまるような姿勢になることがあります。リラックスする時間を持つことも、巻き肩の軽減が期待できるポイントの一つです。
巻き肩を放置するとどうなる?

まず、肩や首の筋肉に負担がかかりやすくなり、慢性的な肩こりや首こりが生じやすくなります。肩が前に出た状態が続くことで、筋肉が常に緊張しやすくなるためです。
また、筋肉の緊張により血流が悪くなると、緊張性の頭痛が起こることもあります。これにより、日常生活に支障が出ることも考えられます。
姿勢への影響も大きく、巻き肩が定着すると猫背が悪化しやすくなります。背中が丸まった姿勢が続くことで、見た目にも影響が出やすく、実年齢より老けて見られてしまうこともあります。
さらに、胸が縮こまった状態が続くと、肺が圧迫されやすくなり、呼吸が浅くなることがあります。酸素の取り込み量が減少することで、疲れやすくなったり、集中力の低下につながったりすることもあるため注意が必要です。
巻き肩を放置すると、肩関節の可動域が狭くなってしまうこともあります。その結果、腕を上げにくくなったり、四十肩・五十肩のような症状につながることも考えられます。
特に女性の場合は、巻き肩によって胸の筋肉が縮まり、バストの位置が下がりやすくなる傾向があります。これにより、実際よりも小さく見えてしまうこともあります。
また、肩が前に出た状態では、神経や血管が圧迫されることがあり、その影響で腕や手にしびれを感じたり、冷えを感じやすくなることもあります。
さらに、巻き肩とともに現れやすいのがストレートネックです。頭が前に突き出す姿勢になることで、首に負担がかかりやすくなり、首の痛みや自律神経の乱れにつながるケースもあるといわれています。
当院の施術方法について

巻き肩の軽減には、いくつかの方法を組み合わせて取り入れることが大切です。以下のような取り組みが、巻き肩の軽減に役立つとされています。
まず、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)の緊張を和らげるために、ストレッチが有効とされています。たとえば、両手を背中側で組み、肩甲骨を寄せながら胸を開くストレッチは、肩が前に巻き込むのを防ぐ効果が期待できます。
次に、背中の筋肉(僧帽筋・菱形筋など)を鍛えることも重要です。背中の筋力を強化することで、肩甲骨が正しい位置に保たれやすくなります。エクササイズバンドなどを使って肩甲骨を引き寄せるような運動が推奨されています。
また、日常生活において姿勢を意識することも欠かせません。デスクワークやスマートフォンの使用が長時間に及ぶ場合は、こまめに姿勢を正すことを心がけましょう。さらに、矯正サポーターなどを活用することで、正しい姿勢の維持をサポートできる可能性があります。
加えて、整骨院や整体などで専門的な施術を受けることも一つの方法です。骨盤の調整や筋膜リリースといった施術により、巻き肩の要因となる筋肉の緊張や骨格の歪みに対してアプローチすることができます。
これらの方法を継続的に取り入れることで、巻き肩の状態が軽減されることが期待されます。
軽減していく上でのポイント

まず、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)の緊張をほぐすストレッチが有効とされています。たとえば、両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せながら胸を開く動作は、肩が前に巻き込まれるのを防ぐ効果が期待できます。
次に、背中の筋力を強化することも大切です。背中の筋肉(僧帽筋・菱形筋など)を鍛えることで、肩甲骨を正しい位置に保ちやすくなります。エクササイズバンドを使用して肩甲骨を引き寄せる運動などが推奨されています。
また、日常生活での姿勢を意識することも重要です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用時には、定期的に姿勢を見直すよう心がけましょう。さらに、矯正サポーターを活用することで、正しい姿勢の維持をサポートすることができます。
加えて、整骨院や整体にて施術を受ける方法もあります。専門家による骨盤の調整や筋膜リリースなどの施術によって、巻き肩の要因となる筋肉の緊張や骨格の歪みにアプローチすることが可能です。
これらの方法を組み合わせて取り入れることで、巻き肩の軽減が期待できます。