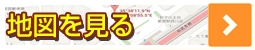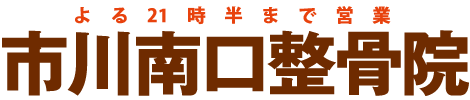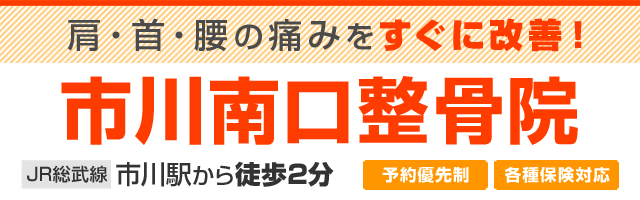こんなお悩みはありませんか?

膝の前側に痛みを感じることがある
運動後やジャンプ・ダッシュで膝の痛みが強くなる
膝下に腫れや膨らみがある
膝を押すと痛みを感じる
階段の上り下りや正座が辛い
スポーツ中に膝に違和感を覚える
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド病は、膝下の脛骨粗面と呼ばれる部位に痛みが現れる成長期特有の症状で、特にスポーツをしている小中学生に多く見られます。主な症状としては、膝を曲げたり、運動後に強くなる膝下の痛みが挙げられます。また、膝下の骨が腫れてきたり、押すと痛みを感じる場合もあります。ジャンプやランニングなどの動作によって症状が悪化することが多く、運動中に違和感や痛みが続く場合には注意が必要です。
膝の骨が突出してくることや、階段の上り下り、正座がつらくなるといったケースも見られます。これらの症状は日常生活にも支障をきたす恐れがあるため、早めに対応することが大切です。症状が進行してしまう前に、専門機関での確認や施術を受けることをおすすめいたします。
症状の現れ方は?

オスグッド病の症状は、膝の前面、特に膝下の脛骨粗面(すねの骨の上部)に痛みや腫れが現れることが特徴です。以下に、主な症状を詳しくご説明いたします。
まず、膝下の痛みが挙げられます。特にジャンプや走ると痛みが強くなることが多く、バスケットボールやサッカーなどのスポーツ後に痛みが増す傾向があります。また、膝を深く曲げたり伸ばしたりする動作で痛みを感じやすくなります。
次に、腫れが見られることがあります。脛骨粗面の部位が腫れることがあり、特に運動後に目立ちやすく、触れるとわかりやすいことが多いです。
膝を触れると痛みを感じることもあります。脛骨粗面を押すと、痛みを感じることがあり、これがオスグッド病の特徴的な兆候です。
また、痛みの強さも症状の一つです。運動や身体的な活動をした後に痛みが強くなることが多く、特に膝に負担がかかるような動き(ジャンプやダッシュ)が引き金になります。休んでいると痛みが軽くなることが一般的です。
さらに、活動の制限も見られることがあります。スポーツや激しい運動を控えることで痛みが和らぎ、腫れも引くことが多いです。
オスグッド病は、成長期の子どもに多く見られ、特に急激に身長が伸びる時期に発生することがよくあります。最初は軽い痛みから始まり、徐々に強くなることがあるため、早期に対処することが重要です。
その他の原因は?

オスグッド病の原因は、膝に繰り返しかかる過剰な負荷にあると考えられています。具体的には、以下のような要素が関与しています。
まず、成長期の骨と腱の不均衡が挙げられます。成長期には骨が急速に伸びますが、筋肉や腱がそれに追いつかないことがあります。特に大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)から膝蓋腱を通じて膝下の脛骨粗面に強い引っ張りがかかることで、膝周辺に過度な負荷が加わり、炎症が起こることがあります。また、成長期の子どもは膝の骨がまだ硬化しきっておらず、軟骨が多く柔らかいため、腱による引っ張りが痛みや炎症につながりやすい状態です。
次に、繰り返しの負荷も原因となります。特にジャンプやダッシュを頻繁に行うスポーツ(バスケットボール、サッカー、陸上競技など)では、膝に継続的な衝撃が加わります。これにより、膝の腱や骨に蓄積された負担がオスグッド病の発症につながることがあります。また、運動の頻度や強度が高すぎると、膝への負荷が増し、発症リスクが高まります。
さらに、筋肉の柔軟性の不足も関係しています。太ももの前側の大腿四頭筋や後ろ側のハムストリングスの筋肉が硬いと、膝への負担が増加しやすくなります。柔軟性が不足することで腱が引っ張られやすくなり、炎症が生じやすくなると考えられています。
また、体の成長バランスの乱れも一因となります。成長の過程で筋肉と骨の発達に不均衡が生じると、筋肉の張力が高まり、膝にかかる負担が増すことで、オスグッド病のリスクが高まる可能性があります。
加えて、遺伝的な要因も無関係ではありません。家族内に同様の症状を経験された方がいる場合、発症しやすい傾向があるとされています。
オスグッド病は、成長期に膝の周囲に過度な負荷がかかることによって起こるため、運動の強度や休養のバランス、ストレッチや筋力トレーニングの実施が予防のポイントになります。
オスグッドを放置するとどうなる?

まず、症状が悪化するおそれがあります。痛みや腫れが持続したり、より強くなったりすることがあり、運動や日常生活で膝を使用するたびに痛みが増してしまうことがあります。最終的には、動作そのものが辛く感じるようになるケースも見られます。
次に、膝への恒常的な負担により、骨や腱に慢性的なダメージが蓄積する可能性があります。特に成長期においては、成長板が関与しているため、過度な負荷によって膝の発育に支障が出る場合があります。
また、運動能力の低下につながることもあります。痛みを避けるために運動を制限すると、筋力が落ち、膝周りの筋肉が弱くなるおそれがあります。その結果、膝の安定性が低下し、将来的なけがのリスクが高まる可能性があります。
さらに、症状が慢性化するリスクもあります。慢性化すると、施術による対応が難しくなることがあり、膝の不安定性や痛みが長期間続くことで、再発や他の膝の問題(例:靭帯や軟骨への影響)につながる可能性があります。
そのほか、日常生活に支障をきたすこともあります。痛みが強くなることで、歩行や階段の上り下りが困難になり、スポーツだけでなく、学校生活や友人との活動にも影響を及ぼすことが考えられます。
このような事態を防ぐためには、放置せずに早期の対処が大切です。安静、アイシング、ストレッチなど、膝への負担を減らす対応を行うことで、症状の軽減が期待され、回復が促されます。症状が長引く場合や悪化が見られる場合には、整形外科での受診を検討されることをおすすめいたします。
当院の施術方法について

オスグッド病の施術方法として、整骨院で行われる一般的な施術についてご紹介いたします。整骨院では、以下のアプローチが取られることが多いです。
1. 手技療法(マッサージ・ストレッチ)
筋肉の緊張をほぐす:太ももの前側(大腿四頭筋)や後ろ側(ハムストリングス)の筋肉をマッサージして柔軟性を高め、膝への負担を軽減します。
関節の可動域を広げる:膝周りの筋肉や関節の柔軟性を向上させるため、ストレッチや軽い矯正を行い、膝の動きをスムーズにします。
2. 電気療法(低周波施術)
痛みの緩和:低周波施術器を使用し、筋肉や神経に軽い電流を流すことで、痛みを和らげたり、筋肉の緊張をほぐしたりします。これにより、膝の炎症が軽減され、痛みの緩和が期待できます。
3. アイシングと温熱療法
冷却:腫れや炎症が強い場合には、冷却により炎症の軽減が期待できます。冷たいパッドや氷を用いて、膝周りを冷やします。
温熱療法:痛みが軽減した後に温熱療法を取り入れることがあります。血流を促進し、筋肉の回復を助けるために、温かい湿布やホットパッドを使用します。
4. テーピング
膝のサポート:膝の周りにテーピングを施すことで、膝の安定性を高め、痛みの軽減が期待できます。テーピングによって膝にかかる負担を減らし、動作時の痛みを防ぐことができます。
5. 姿勢や動作の指導
歩き方や運動フォームの見直し:膝に余分な負担がかからないように、姿勢や動作についての指導を行います。運動や日常生活において膝にかかるストレスを軽減するためのアドバイスも行われます。
6. 運動療法(リハビリ)
筋力トレーニング:膝を支える筋肉を強化するための運動指導が行われます。特に、大腿四頭筋やハムストリングスの強化が重要です。
柔軟性の維持:膝周りの柔軟性を保つために、ストレッチやエクササイズを取り入れます。
7. 生活習慣のアドバイス
休養の指導:過度な運動や膝に過剰な負担をかけないよう、適切な休養や運動量の調整についてアドバイスを行います。
整骨院での施術は、痛みや炎症の緩和を目的としており、症状の軽減が期待できます。ただし、オスグッド病は成長に伴って自然に回復することが多いため、整骨院での施術と並行して安静を保つことが大切です。症状が悪化する前に、早期にご相談されることをおすすめいたします。
改善していく上でのポイント

オスグッド病の症状を軽減するためのポイントは、以下のように段階的に取り組むことが大切です。
1. 安静と休養
運動を控える:膝に過度な負担がかかる運動(ジャンプやダッシュなど)は控え、痛みが落ち着くまで休養をとることが大切です。スポーツを再開する際には、徐々に負荷を増やしていくようにしましょう。
膝を守る:膝を無理に使わないよう注意し、できる限り安静を保ちます。
2. アイシングと冷却
炎症の軽減が期待できる:痛みが強い場合や膝に腫れが見られる場合には、アイスパックや冷却ジェルを使用して膝を冷やします。冷却することで、炎症の軽減や痛みの緩和が期待できます。
目安として1回20分程度:冷却は1回20分程度を目安に行い、間隔を空けて繰り返します。
3. ストレッチと柔軟性の向上
筋肉の柔軟性を保つ:太もも(特に大腿四頭筋)やハムストリングスの柔軟性を保つことで、膝への負担を軽減することができます。日常的にストレッチを取り入れ、柔軟性の維持を心がけましょう。
関節の可動域を広げる:膝周辺の筋肉や靭帯の柔軟性を保つことも重要です。
4. 筋力強化
膝を支える筋肉の強化:膝を支える筋肉(特に大腿四頭筋やハムストリングス)を鍛えることで、再発の予防が期待できます。筋力トレーニングやリハビリを通じて、膝周りの筋肉をしっかりと強化していきます。
運動後のケアも大切:筋肉を使用した後は、ストレッチや軽いマッサージを行い、疲労の軽減に努めましょう。
5. サポーターやテーピング
膝のサポート:膝にかかる負担を軽減するため、膝用サポーターやテーピングを活用することで、痛みの緩和や膝の安定性の維持が期待できます。
適切なサイズ選び:使用する際は、膝に合ったサイズで圧迫が過剰にならないように注意します。
6. 生活習慣の見直し
体重の管理:膝への負担を減らすためには、適正な体重を維持することが大切です。過度な体重は膝へのストレスを増加させます。
運動量の調整:過剰な運動やジャンプ、ダッシュなどは控え、膝に優しい運動(ウォーキングや水泳など)を選ぶようにしましょう。
7. 医師の診断と指導
定期的なチェックを受ける:症状が続く場合や痛みが強い場合には、整形外科での定期的な診断を受けることが大切です。必要に応じてリハビリや整骨院での施術を受けることで、症状の軽減が期待できます。
8. 焦らず徐々に回復を目指す
無理をしない:症状が軽減した場合でも、すぐに激しい運動を再開するのではなく、徐々に運動を取り入れて、膝への負担を段階的に増やしていくことが重要です。